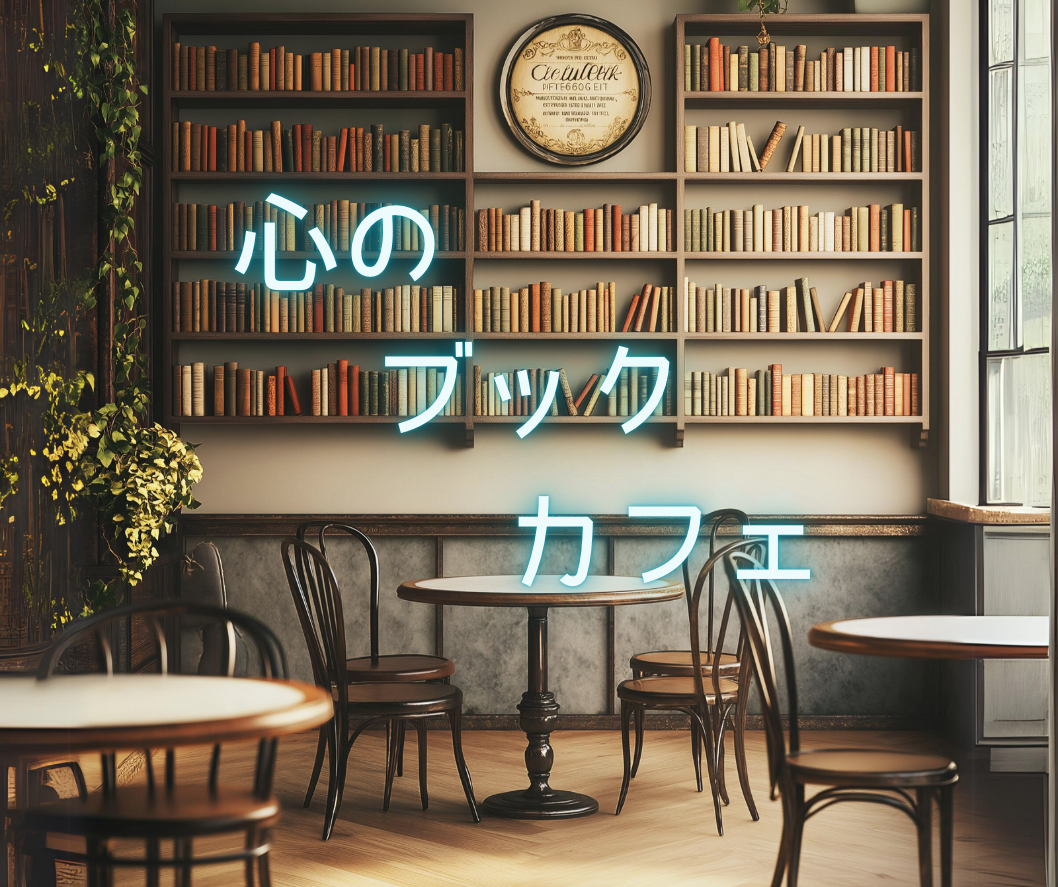今回のニュース 2024/9/10
不安、怖い」の強迫観念が消えなくてつらいとき...試してほしい8つのアイデア yahooニュースより
強迫観念に悩まされているときの対処法として、以下の8つのアイデアが紹介されていいました。
これらの方法は、強迫観念から注意をそらし、別のことに集中することで不安や恐怖を和らげる効果があります。個人に合った方法を見つけて実践することが大切です。また、症状が重い場合は専門家に相談することをお勧めします。
- 体を動かす (散歩、料理など)
- 興味のあることに関心を向ける (読書など)
- ラジオのトーク番組を聴く
- 強迫観念を茶化す (ギャグや替え歌にするなど)
- やることリストを作成し、具体的な行動を決めておく
- おなかをへこませて30秒キープする
- 舌でアルファベットを空書きする
- 体の一部に意識を向ける
強迫症って、どんな病気なのでしょうか? 「手を何度も洗ってしまう」「ドアの鍵を何度も確認してしまう」といった行動を繰り返す。そんな症状を聞いたことがある人も多いかもしれません。しかし、強迫症はそれだけではありません。
精神科医の野間利昌先生によると、強迫症は「強迫観念」または「強迫行為」、あるいはその両方が存在する状態を指します。これらの症状により、日常生活や人間関係に支障をきたすほど時間を浪費してしまうのが特徴です。
強迫観念の内容は人それぞれで、不安や恐怖に結びつくことが多いのですが、時には「しっくりこない感覚」程度のこともあります。以前は何気なくできていたことが、突然「本当にそれで良いのか」と確信が持てなくなるのです。
そして、その不快な感覚を消そうとして、または最初から避けようとして「強迫行為」を行うようになります。しかし、皮肉なことに、強迫行為を繰り返せば繰り返すほど、本当にやれたのか自信が持てなくなり、さらに不安が募る悪循環に陥ってしまいます。
強迫症の平均的な発症時期は20歳前後ですが、実際には児童期から60代以上まで幅広い年齢層で発症する可能性があります。生涯有病率は1〜2%程度で、約50人に1人が経験する比較的一般的な精神疾患と言えます。
強迫症の治療が遅れる原因としては、以下のようなものが挙げられます:
1. 症状を恥ずかしく感じる:
多くの患者さんは、自分の症状を他人に知られたくないと考えます。「変な人だと思われるのではないか」という不安から、症状を隠そうとしてしまいます。
2. 精神科受診へのためらい:
精神科や心療内科を受診することに抵抗を感じる人も少なくありません。「精神科に行くほどではない」と自分で判断してしまうケースも多いのです。
3. 症状に慣れてしまう:
長年症状と付き合ううちに、「これが普通」と思い込んでしまうことがあります。そのため、治療の必要性を感じにくくなってしまいます。
では、いつ治療を始めるべきなのでしょうか?野間先生は、「治したい」という本人の意思が最も重要だと強調します。特に、症状が急激に悪化したときは、治療のチャンスと捉えることができます。症状の苦しさが治療への動機づけとなるからです。
強迫症の治療には、主に薬物療法と行動療法
薬物療法では、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)が主に使用されます。
一方、行動療法の中心となるのが曝露反応妨害法(エクスポージャー)です。
曝露反応妨害法とは、恐怖や不安を感じる状況に意図的に身を置き、そこで強迫行為をせずにいることで、不安に慣れていく方法です。例えば、手洗いの強迫がある場合、普段より手を洗わない時間を少しずつ延ばしていくといった具合です。
治療の目標は、不安や恐怖に「慣れる」ことです。野間先生は、「グレー」の状態を受け入れることが重要だと説明します。つまり、100%安全や完璧を求めるのではなく、ある程度の不確実性や不完全さを許容できるようになることが治療の鍵となります。
効果的な治療を進めるためには、以下の点が重要です:
1. 医師との協力関係:医師によってはカウンセラーに一任することがあります。
治療は医師と患者さんの共同作業です。お互いに信頼関係を築き、率直なコミュニケーションを取ることが大切です。
2. ホームワークの実践:
診察室での治療だけでなく、日常生活の中で医師から指示されたホームワーク(曝露練習など)を実践することが重要です。
3. 定期的な受診と報告:
治療の進捗を確認し、必要に応じて方針を調整するため、定期的な受診と症状の報告が欠かせません。
患者さんに求められる心構えとしては、以下のようなものがあります:
1. 医師のアドバイスに素直に従う:
自分の考えにこだわりすぎず、専門家である医師のアドバイスを素直に受け入れる姿勢が大切です。
2. 継続的な実践:
治療効果はすぐには現れないことが多いため、根気強く継続することが重要です。
3. 小さな進歩を認める:
完璧を求めるのではなく、小さな進歩や改善を認め、自分を褒めることも大切です。
結論として、強迫症は決して珍しい病気ではなく、適切な治療を受ければ改善が期待できる疾患です。
症状に悩んでいる方は、恥ずかしがらずに専門医に相談することをおすすめします。
治療には時間がかかることもありますが、医師と協力しながら粘り強く取り組むことで、多くの患者さんが症状の改善を実感しています。
強迫症との闘いは、不安や恐怖と向き合い、それらを受け入れていく過程でもあります。
この記事が、強迫症に悩む方々やその家族の方々にとって、希望の光となれば幸いです。
私の娘も強迫性障害を患っています。気がついたら、なっていました。最初のころはとにかく落ち着かず、
しんどい、しんどいと一日中、私に泣きついてきました。
どうしたらいいか分かりませんでした。暴れたりもしました、○のうともしました。
二人で一緒に○のうとも言われました。家族みんなが辛かったです。本人が一番しんどかったと思います。
寝たらしんどいことを忘れられる。寝る。起きた時にまた起こる恐怖感は辛かったと思います。
症状が出たのはコロナ禍で、同じような患者さんで溢れており、、特に18歳以下の
受診できる病院は限られていました。しかも強迫性障害のことを分かっておられる先生が少なかったです。
それでも、どうにか有名な先生の病院が見つかり、有名な先生はもう新しい患者さんは診ていないという
ことで、別のお医者さんでした(性格が悪い最悪な先生なので省略)。
すごいのはカウンセラーさんです。話も分かりやすく、子供も納得して聞いていました。
子供の心を掴むのも上手なんだと思います。お医者さんや看護師さんには暴言を吐いてましたから。
まず、1回目でかなり症状が改善しました。正直、半減したと思います。
すごく驚いたのを覚えています。
しかし、もちろんそう簡単に良くはなりませんんが、バイブルとなる本を購入し、忘れそうになったら
読み返して、徐々にに自分をコントロールできるようになってきました。
今では、かなり普通の生活をしています。しかし、新しく決まった専門学校にはまだ行けていません。
でも、将来のことや自分の意思がしっかりしてるので、安心はしています。
まだまだ、目は離せませんが、ゆっくり進んでいこうとしています。
最後に先生の紹介
野間利昌医師(今回のニュース記事の先生です)
1. 専門分野:
- 精神科医、特に強迫症・強迫性障害の治療に特化
- 認知行動療法(CBT)を中心とした個別治療プランを提供
2. 現職:
- セレーナメンタルクリニック院長
- 年間400人以上の患者を診療
3. 経歴:
- 千葉県出身
- 東京外国語大学卒業後、山形大学医学部卒業
- 千葉大学精神神経科で研鑽を積む
- 千葉大学医学部附属病院で強迫性障害外来担当
- 2007年にセレーナメンタルクリニックを開設
4. 著書:
- 『強迫症/強迫性障害をワークで治す本』(大和出版)
- 曝露反応妨害法(ERP)を用いた自宅での実践方法を解説
- 患者の自発的な治療への取り組みを重視
野間医師は、強迫症治療の専門家として高い評価を受け、著書や診療を通じて多くの患者に貢献しています
AD
スポンサーリンク
- 『強迫症/強迫性障害をワークで治す本』(大和出版